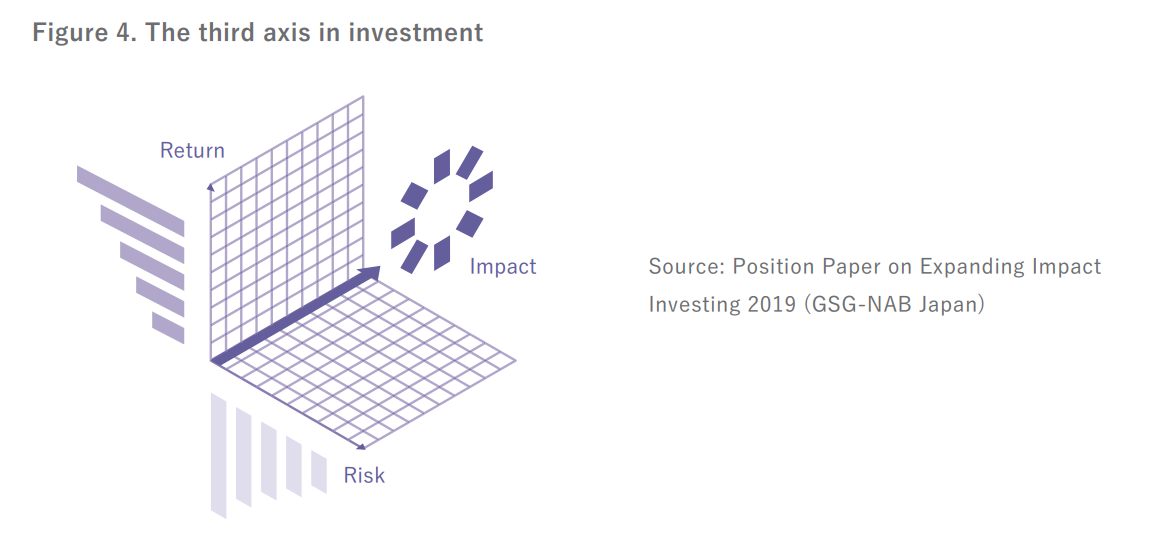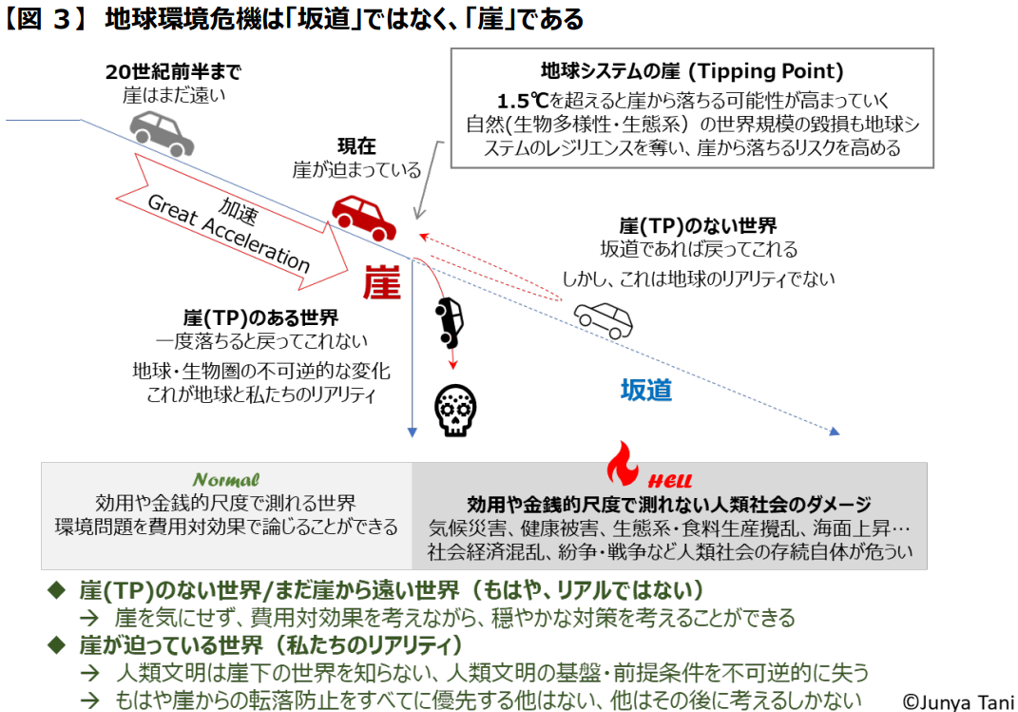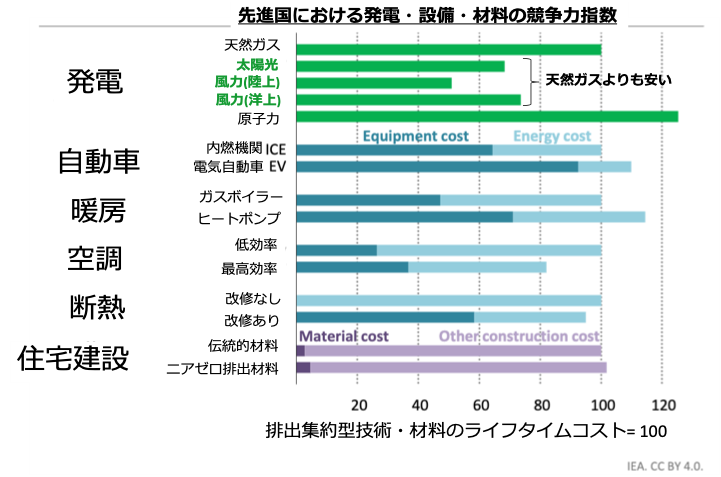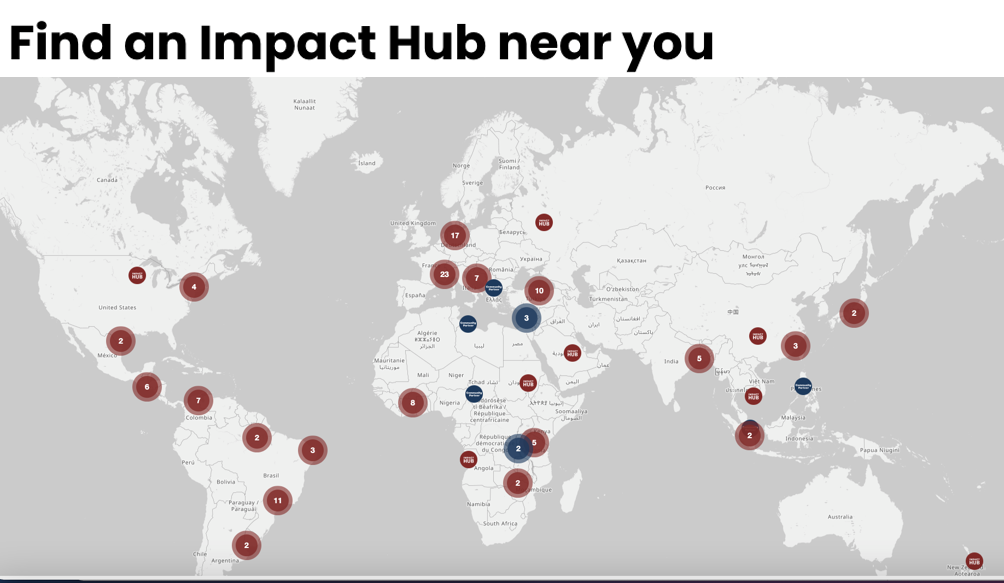
(前回は、インパクトファイナンスについて「第1回:マーケットの変遷と注目される理由」 )
5.国内外での対応や最新動向――制度・市場・標準化の進化と現場課題
■ 国際動向:規制と現場での実装
欧州連合(EU)は、CSRD(企業サステナビリティ報告指令)、EUタクソノミー、SFDR(サステナブルファイナンス開示規則)などによって、社会・環境インパクトの厳格な開示義務化を先導してきました。CSRDによるダブルマテリアリティの導入により、企業・金融機関は財務・社会両面からの説明責任が強化されています。2024年には、現場負担の軽減を目的としたオムニバス法案(Omnibus Directive)が提案され、中小企業や一部非上場企業のCSRD段階的適用やガイダンス再整理、報告義務の緩和が議論されています。